
目打ち(めうち)の意味【料理の雑学、豆知識】和食の料理用語集
目打ち(めうち) 和食の料理用語集 目打ち(めうち)とは ① 白魚や公魚(わかさぎ)などの小さな魚を数匹並べて、目に細い竹串や楊枝(よ...

目打ち(めうち) 和食の料理用語集 目打ち(めうち)とは ① 白魚や公魚(わかさぎ)などの小さな魚を数匹並べて、目に細い竹串や楊枝(よ...

芽芋(めいも) 和食の料理用語集 芽芋(めいも)とは 里芋の葉柄(ようへい)部を軟化栽培して50㎝程度のびた新芽を軟白したもので、芋茎...

別足(べっそく) 和食の料理用語集 別足(べっそく)とは 雉(きじ)などの「もも」のことです。 【関連】 ≫和食の献立...

へしこ漬け 和食の料理用語集 「へしこ漬け」とは 福井県の郷土料理で、豊漁期に作る魚の漬物のことです。 内臓を除いた鰯(いわし)...

折ぎ折り、剥ぎ折り(へぎおり) 和食の料理用語集 折ぎ折り、剥ぎ折り(へぎおり)とは へぎ板で作った折りのことです。 ≫折ぎ板、...

折ぎ板、剥ぎ板(へぎいた)の意味【和食の料理用語集】折ぎ板、剥ぎ板とは杉や檜(ひのき)などの木材を薄く板状に剥いだ(はいだ)物のことで、「へぎ」ともいいます。ある程度の厚みを持たせた物は折敷(おしき)や折り箱を作るときに用い、ごく薄い製品(薄板ともいう)は調理に使ったり、店舗によって料理の献立を書いたりします。

折ぎ、剥ぎ(へぎ) 和食の料理用語集 折ぎ、剥ぎの意味4つ ① 薄く削り取ること、または、へぐことや剥ぎ切り(へぎぎり)を意味します。...

繁縷(はこべ、はこべら) 和食の料理用語集 繁縷(はこべ、はこべら)とは なでしこ科の2年草で「春の七草」のひとつです。 朝日に...

博打汁(ばくちじる) 和食の料理用語集 博打汁(ばくちじる)とは 汁物のひとつで、豆腐をさいの目に切って汁の実にした料理です。 ...
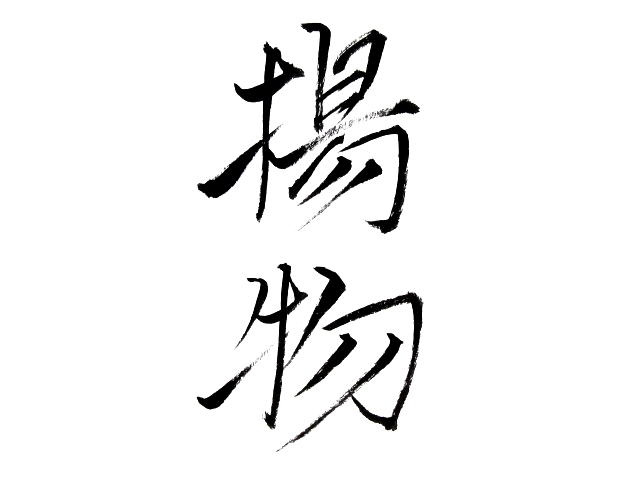
白妙揚げ(しろたえあげ)とは、揚げ物のひとつで片栗粉に泡立てた卵白を加えてふんわりとさせ、この衣を材料につけて揚げたものです。また、別名を白扇揚げ(はくせんあげ)といいます。
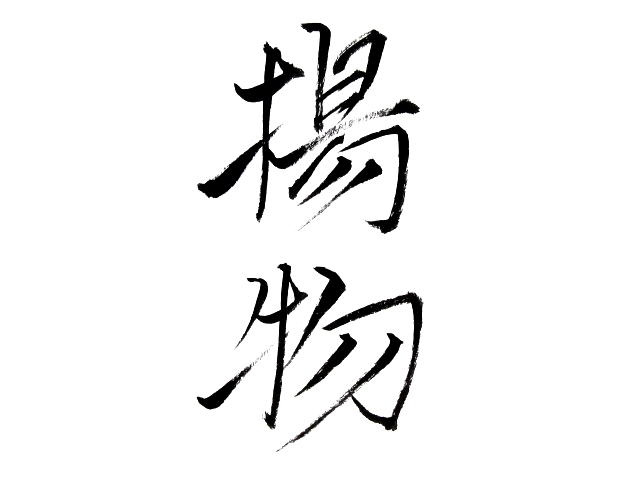
白扇揚げ(はくせんあげ)とは、揚げ物のひとつで、片栗粉に泡立てた卵白を加えてふんわりとさせ、この衣を材料につけて揚げたものです。そして、別名を白妙揚げ(しろたえあげ)といいます。
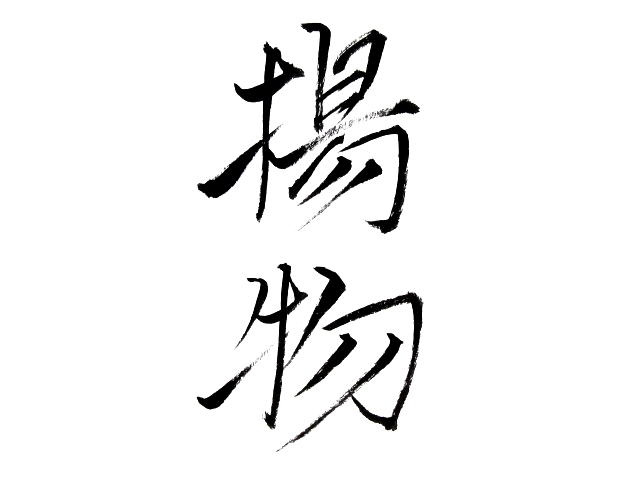
博多揚げ(はかたあげ)とは、色が異なる材料を重ねた揚げ物のことで、はさみ揚げと同じような料理です。料理用語の博多とは、博多帯の織り柄のように2種類以上の色が違う材料を重ねて、切り口がしま目になるように細工した料理の名称で、切り口が見えるように盛りつけます。刺身の場合はイカやキスなどの身が薄い材料を使うことが多く、昆布じめにした白身魚にゆでた菜の花や菊花などを挟んで軽く重しをかけて作ります。そして、この料理は「博多押し」と呼ぶことが多く、加減酢をかけて酢の物としても使えます。
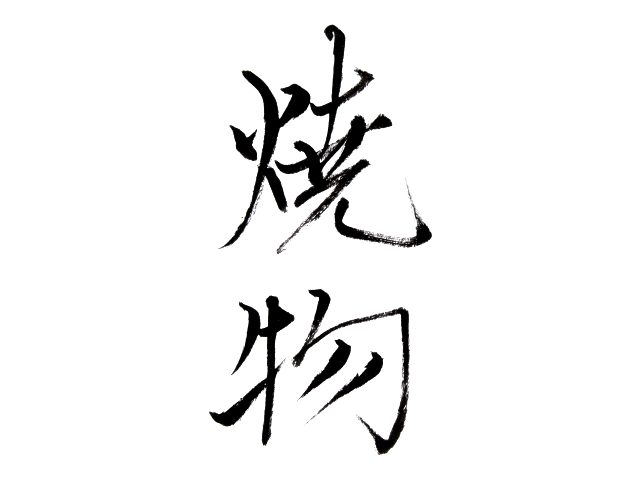
博多焼き(はかたやき) 和食の料理用語集 博多焼き(はかたやき)とは はさみ焼きと同じような焼き物で、作り方も似ています。 博多とは...

梅肉酢(ばいにくず)の意味 和食の料理用語集 梅肉酢(ばいにくず)とは 梅肉に砂糖や酒、みりんを加えてのばしたり、甘酢でのばして味をと...

梅肉醤油(ばいにくじょうゆ) 和食の料理用語集 梅肉醤油(ばいにくじょうゆ)とは 梅肉に醤油を合わせたもので、和え物の衣や刺身のつけ醤...

梅肉和え(ばいにくあえ) 和食の料理用語集 梅肉和え(ばいにくあえ)とは 和え物のひとつで、梅干しの果肉で材料を和えたものです。 ...

梅肉とは(ばいにく) 和食の料理用語集 梅肉とは(ばいにく)とは 梅の果肉のことです。 梅干しをそのまま裏ごしたものや、鍋に並べ...

和食の料理用語集【梅花玉子(ばいかたまご)とは】玉子細工のひとつで、梅の花の形に似せて作るところから、この名があります。

春の七草、薺(なずな) 和食の料理用語集 薺(なずな)とは あぶらな科の2年草で、別名を「ぺんぺん草、しゃみせん草」といい春の七草のひ...

茄子玉子(なすたまご)の意味 和食の料理用語集 茄子玉子(なすたまご)とは 細工玉子のひとつで、ゆで玉子を青の色素で「るり色」に染め、...

夏~秋が旬の茄子(なす) 和食の料理用語集 茄子(なす) なす科の一年草で、原産国はインドとされます。 そして、なすの学名にはリ...

梨割り(なしわり) 和食の料理用語集 梨割り(なしわり)とは 材料をたて方向にして、真半分に割ることをいいます。 (例)鯛の頭や...

中砥(なかと) 和食の料理用語集 中砥(なかと)とは 砥石(といし)の一種で、荒砥よりも質が密にできており、きめ細かいのが特徴です。 ...

長月(ながつき) 和食の料理用語集 長月(ながつき)とは 9月の別名で、日本料理の献立には9月ではなく「長月」と書くことが多いです。 ...