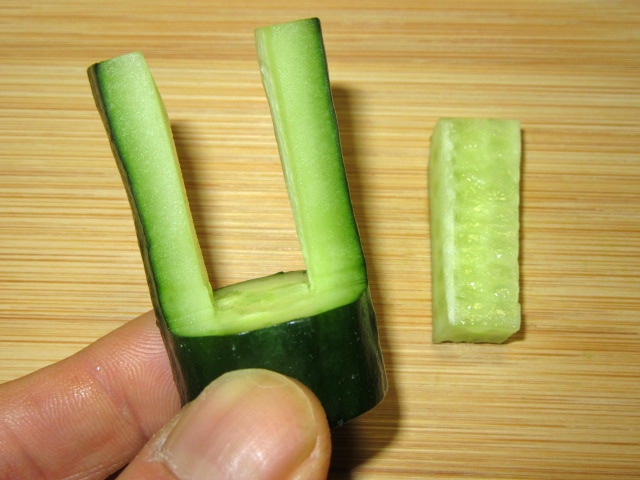【赤味噌仕立ての吸い物】

今回は赤だしの調味料割合をご紹介したいと思います。
味噌汁は種類によって味と風味が異なりますので割合で作ることは少ないですが、風邪などで体調を崩しているときは舌の感覚が鈍ります。
そのような場合に、ある程度の分量を決めておくと味のぶれが少なくなりますので、参考にされてはいかがでしょうか。
和食の配合、調味料割合
赤味噌仕立てのお吸い物
【調味料の割合】
| だし | 1000㏄ |
| 赤味噌(八丁味噌) | 120g |
| 濃口醤油 | 少量 |
| みりん | 少量 |
| 追い鰹 | 適量 |
赤だしの割合一例です。
赤だしや他の味噌汁に追い鰹をしたあとは、澄んだ汁とは違って鰹の粉が見えませんのでザルで漉してください。
※ 鰹だしを漉すときのようにネル地やキッチンペーパーを使うと、味噌の粒も一緒にとれてしまいますから、必ずザルで漉してください。
また、濃口醤油とみりんはコクと香りを出すために加えますので、旨味が強い味噌のときは入れなくても大丈夫です。
そして、いつも使っている味噌で割合を決めておくと、一度にたくさん合わせるときの目安にもなり、手早く作ることができます。
赤味噌煮とは
色によって分類した味噌の種類名で、白味噌の対語として用いられています。
江戸味噌、津軽味噌、仙台味噌、佐渡味噌、田舎味噌、豆味噌など、赤褐色の強い味噌を総称してこの名で呼びます。
赤味噌の赤褐色は、大豆を蒸煮(じょうしゃ)するときに生じるもので、長時間蒸煮したり、高温で蒸煮したりすることによって色の濃さが増します。
これは、アミノカルボニル反応を利用したものです。
また、熟成温度が高かったり、熟成期間が長いと味噌に対する色の濃さは更に進みます。
アミノカルボニル反応とは、食品に生じる非酵素的褐色現象の一種。フランスの研究者「メイラード」が1912年に明らかにしたもので、発見者の名をとって「メイラード反応」とも呼ばれる。これは、還元糖のカルボニル基とアミノ酸のアミノ基が化学反応を起こして、褐色物質の「メラノイジン」を作る反応であり、メラノイジンの名をとって「メラノイジン反応」ともいう。この褐色現象は、pH、温度、金属イオンの影響を受けやすく、反応によって生じるアミノ酸の損失など、栄養的には好ましくない点もあるが、一方でショウユやミソの色など、食品に好ましい色をつけたり、香りをつけたりする役割を持っている。焼き物など高温加熱の調理によってアミノカルボニル反応が起こると、食品は褐色の被膜を作り、独特の香りを発生させると同時に、その見た目や香ばしい匂いから食欲をそそる効果が期待できる。また、同時に抗酸化性も発言してくれる。パン、ケーキ、ちくわ、せんべい、かば焼きなどは、焼き上げの調理作業中にこの反応が起こるため、風味や色調が加わって食欲増進につながる。


【関連】
他の割合につきましては≫「和食の調味料割合と配ごう一覧」に掲載しておりますので参考にされてはいかがでしょうか。