
焼き物の種類と関連の料理用語50音順一覧表
焼き物レシピの関連 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 焼き物の種類と関連用語一覧表 ■一覧表内の青い文字(リンク)から各料理や献...
【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。

焼き物レシピの関連 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 焼き物の種類と関連用語一覧表 ■一覧表内の青い文字(リンク)から各料理や献...

和え物レシピの関連 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 和え物の種類と関連用語一覧表 ■一覧表内の青い文字(リンク)から各料理や献...

蒸し物レシピの関連 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 蒸し物の種類と関連用語一覧表 ■一覧表内の青い文字(リンク)から各料理や献...

揚げ物レシピの関連 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 揚げ物の種類と関連用語一覧表 ■一覧表内の青い文字(リンク)から各料理や献...

酢の物レシピの関連 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 酢の物の種類と関連用語一覧表 ■一覧表内の青い文字(リンク)から各料理や献...

鍋物レシピの関連 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 鍋料理の種類と関連用語一覧表 ■一覧表内の青い文字(リンク)から各料理や献立...

ご飯物レシピの関連 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 ご飯物の種類と関連用語一覧表 ■一覧表内の青い文字(リンク)から各料理や献...

料理の食材集 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 赤貝(あかがい) フネガイ科、サルボウ属の2枚貝で「赤玉、本玉」とも呼ばれます。...

磨き河豚(みがきふぐ) 和食の料理用語集 磨き河豚(みがきふぐ)とは 内臓を取り除いて水洗いした「ふぐ」のことです。 ≫ふぐの雑...

今回は日本人が食事をする際にお茶碗を持って食べる理由と和食(日本料理)の盛りつけや器などの決まり事についてご紹介したいと思います。最近は欧米の文化が日本でも取り入れられ、お茶碗を持たなくて済むことが増えています。では、なぜ器を手で持って食べないと行儀が良くないと親が子に教えるのでしょうか。
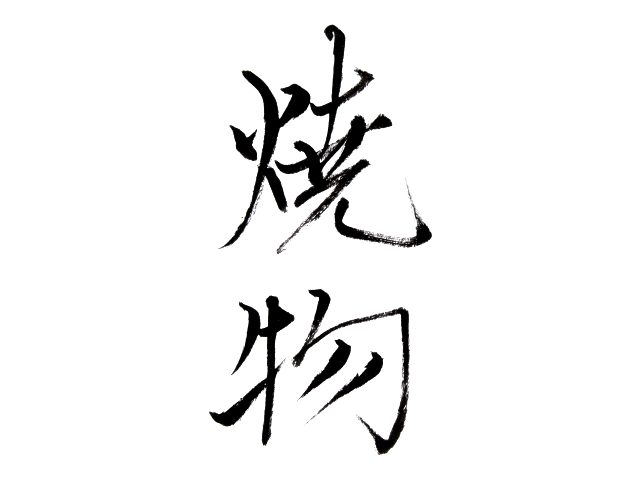
「甘だいの松笠焼き」の意味 和食の料理用語集 甘鯛の松笠焼き(あまだいのまつかさやき) 甘鯛を皮つきのまま焼いて表面のうろこを松ぼっく...

5月5日・端午の節句の粽(ちまき)今回は子供の日に粽を食べる理由と歴史などをご紹介したいと思いますので料理の豆知識としてお役立てください。粽は米粉、もち米、うるち米などで作ったもちを長細い円すい形または三角形にととのえ、ササやマコモなどの葉で巻いてイグサで縛ったものが一般的です。

「和食のあわせ酢5つ」土佐酢、ポン酢、加減酢、二杯酢、三杯酢、今回は酢の物を作るときに使う酢の種類や用語の意味、由来などをご紹介したいと思いますのでお役立てください。

和食の料理用語集【ぼんぼりとは】ほのかな薄紅色に仕上げた料理の総称で、白身魚や海老の繊維を桃色に色付けした「でんぶ」をさす場合が多く、巻き寿司の具やひな祭りの献立によく使います。

料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】■本サイトの献立名では日本語として読みやすくするために送り仮名をつけておりますが、実際には漢字のみの表記が多いです。座付き物とは?酒席の献立として一番はじめに出す料理のことで、座に付く ⇒

1/15に小豆がゆを食べる理由とは「小豆がゆの由来」小豆がゆは1月15日の「小正月」を祝って食べられる料理で、別名を「15日がゆ」ともいい、元来は農耕神事としての習慣でした。そして、小豆がゆを炊くときに使う粥杖(かゆつえ)と呼ばれる棒で、その年の吉凶を占い、五穀豊穣と子孫繁栄を神に願うという意味が込められています。

料理の雑学、豆知識■あんかけとは、くずあんをかけて調理したものや、中国料理のように水とき片くり粉を煮汁に加えてとろみをつけた料理の総称です。あんかけ料理の利点3つ① 粘性を持つあんを調理した食材にかけて表面を覆うことで、乾燥を防ぐと同時に料理が冷めにくくなります。②

御節料理(おせちりょうり)とは節会(せちえ)の供御(くご・ぐご)、供饌(ぐせん)で節句料理のことです。■節会とは日本の宮廷の祝い日に行われる饗宴を伴う公式行事をいいます。■供御とは天皇や皇族の食事のことで供饌は神に供え物をする行為をさし、供える食べ物などは神饌(しんせん)といいます。

正月料理「一の重」~「与の重」今回は、おせち料理を作るときに、ぞれぞれの重箱に入れる料理の種類と主な順番をご紹介したいと思いますので、節句料理の献立や和食調理にお役立てください。

料理の雑学【お正月の豆知識】今回は、おせちと正月に関連した料理の語源や意味、由来、そして幸福になるための願いなどを集めましたので、年末、年始の家族団らんや和食調理にお役立ていただければ幸いです。

田作り(たつくり、たづくり)の語源、意味、由来 正月料理の雑学、豆知識 【田作り】とは 片口いわしの幼魚の乾燥品のことで、別名を「...

和食の語源、意味、由来【おせち料理の雑学、豆知識】今回は、おせち料理に数の子や鰊(にしん)を使う理由をご紹介したいと思いますので、お正月の家族だんらんや、和食調理にお役立てください。

おせち料理レシピや祝い肴の関連記事 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 黒豆を使う意味と理由 元来「まめ」には丈夫や健康という意味...

和食の語源、意味、由来「おせち料理の雑学、豆知識」今回は、おせち料理に鰤(ぶり)を使う理由をご紹介したいと思いますので、お正月の家族だんらんや、和食調理にお役立てください。