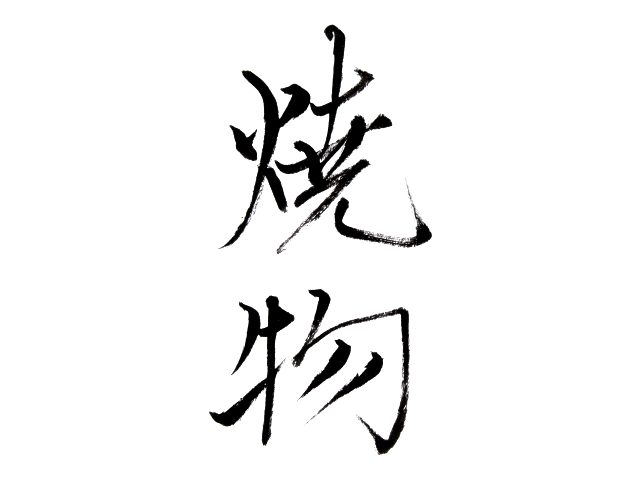
甘だいの松笠焼きとは【和食の焼き物、作り方と料理用語集】
「甘だいの松笠焼き」の意味 和食の料理用語集 甘鯛の松笠焼き(あまだいのまつかさやき) 甘鯛を皮つきのまま焼いて表面のうろこを松ぼっく...
【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。
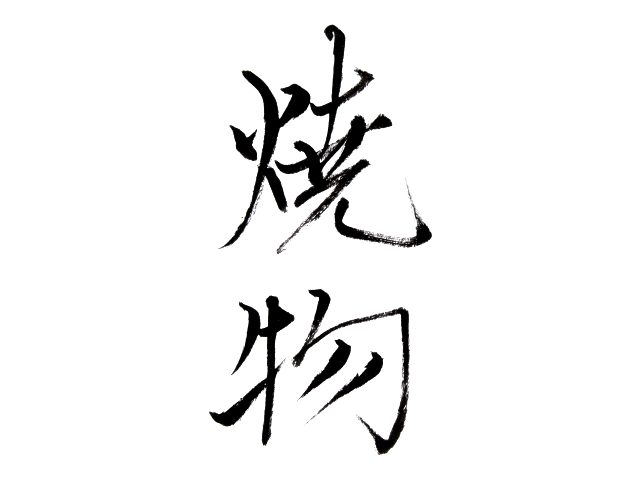
「甘だいの松笠焼き」の意味 和食の料理用語集 甘鯛の松笠焼き(あまだいのまつかさやき) 甘鯛を皮つきのまま焼いて表面のうろこを松ぼっく...

牡蠣(かき)割り、または牡蠣むきとは、牡蠣の身を取り出す専用の調理道具です。【使い方】金具を殻と殻の間に差し込んで平たいほうに付いている貝柱をはずすと身が取り出せます。【牡蠣のむき方の詳しい手順】

料理用語の東寺(とうじ)の語源・意味・由来◆料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】東寺とは?日本料理の献立名のひとつで、湯葉を用いた料理の総称です。この東寺という言葉は料理用語の中では湯葉の別名として多く使われ、

料理の雑学、豆知識・捻り胡麻(ひねりごま)の意味 和食の献立 【料理用語集】 捻り胡麻とは 鍋でいったゴマを指先でつまんでそのゴマをひ...

料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】葛を引くとは?▶葛煮(くずに)とは?▶葛叩き(くずたたき)の意味 ▶葛取り(くずどり)の意味【郷土料理】▶簡単ごま豆腐レシピ【練らずに食感を加える方法】▶ごま豆腐の動画を見る

料理の雑学、豆知識 【和食の料理用語集】 アミノカルボニル反応とは? 食品に生じる非酵素的褐色現象の一種。フランスの研究者「メイラード...

今回は鍋物やご飯物を食べるときに使う「ちりれんげ」の歴史と語源をご紹介したいと思いますので、料理雑学の参考にされてはいかがでしょうか。料理の雑学、豆知識■ちりれんげとは■ちりれんげの歴史■ちりれんげの語源、由来【関連】鍋料理を作る時の調味料割合、煮汁や鍋だしの配合50音順一覧

天ぷら 180度 こげる!今回は天ぷらや唐揚げなどの揚げ物の適温が180℃といわれる理由をご紹介したいと思いますので、和食調理にお役立てください。天ぷら油の適温が180℃といわれる理由とは?これは昔の油の精製度が

香の物とは漬物の総称として使われる言葉で、香木のかおりを楽しむ際に「たくあん」をかじって臭覚を取り戻したということから、この名があります。香の物の詳しい内容につきましては≫茶懐石料理で出される香の物の語源、意味、由来に掲載しておりますので参考にされてはいかがでしょうか。

青ねぎと白ねぎの違い 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 青葱(あおねぎ)とは 「葉ネギ」と呼ばれるもので、緑色の葉の部分が長くて...

【料理の意味】今回は料理の本来の意味と、現在使われている主な言葉をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。【語意】≫料理という言葉には「はかりおさめる」という意味があります。本来の言葉の意味とは≫【関連】調理の意味とは

【和食の基本、食材の切り方】 今回は和食の基本となります、野菜の切り方や調理例などをご紹介したいと思います。 和食(日本料理)は...

今回は料理の「さしすせそ」と言われる調味料を入れる順番の理由を3つご紹介したいと思いますので、料理作りにお役立てください。味つけの基本と順番3つの理由

【2つのきんしたまごの意味】今回は、うす焼き玉子の「金紙」と「錦糸」の違いをご紹介したいと思いますので、献立を書く場合や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。和食の料理用語集【金紙玉子と錦糸玉子の違いとは!】

【鱧(はも)の雑学、豆知識】今回は鱧の名がつけられた由来をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。鱧の名の語源、意味、由来■ 鱧の生態と特徴■鱧が京都や大阪で多く使われる理由

今回は茶懐石料理の献立に使われる葉蓋をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。【和食の料理用語集】葉蓋(はぶた)とは

石川芋 きぬかつぎ【料理の雑学、豆知識】衣被(きぬかつぎ)とは?きぬかつぎの語源を見る■石川芋(いしかわいも)とは?サトイモの早生品種の石川早生(いしかわわせ)のことで、緑茎の子イモ用品種です。石川小芋・石川子芋(いしかわこいも)とも呼ばれます。

「和食のあわせ酢5つ」土佐酢、ポン酢、加減酢、二杯酢、三杯酢、今回は酢の物を作るときに使う酢の種類や用語の意味、由来などをご紹介したいと思いますのでお役立てください。

冬瓜の語源、由来、冬瓜は夏の食材として有名ですが、そのまま切らずに置いておくと冬まで保存が利くということから冬の瓜⇒「冬瓜」と呼ばれています。

今回は焼き物を作るときの串の打ち方を集めましたので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。和食の焼き物手法、串の打ち方と名称一覧■各串打ち方法に移動いたします。

あしらいとは、器に盛りつけた料理を一層引き立てる目的で添える「野菜類や花」などの総称です。また「あしらう」という言葉には、とり合わせるといった意味があり、季節の葉を料理にあしらう、飾りに花をあしらう等の使い方をします。【関連】和食の飾り切り手順一覧 ■≫食材の下処理方法一覧を見る
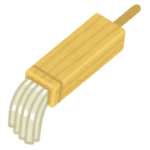
心太(ところてん)の語源、意味、由来 和食の料理用語集 心太(ところてん)とは 寒天を煮溶かして冷やし固めたものを「てんつき」という道...

和食の椀物料理用語集【吸い物、汁物の語源、意味、由来50音順一覧】各料理用語に移動いたします。あ段~わ段【関連】■吸い物が美味しく感じる塩分濃度の理由と簡単な割合■吸い物、汁物レシピ関連一覧■椀物の献立一覧へ

刺身の手法と造りの名称、向付料理用語集【語源、意味、由来50音順一覧】各料理用語に移動いたします。あ段~わ段【関連】さばく、おろす、開くのちがいとは■刺身の手法関連記事■刺身に使える飾り切りとわさび台の切り方一覧■大根けんのむき方、桂むきのコツ5つ■氷器の作り方